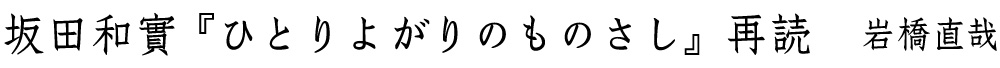
2 ドゴン族の柱と扉

ドゴン族、アフリカの「白い」モノ、もまた「古道具坂田」といえばこれ、という印象が強いのではないだろうか。坂田さんは1973年に開店した「古道具坂田」で、1977年から2011年までに合計26回のテーマ展を行なっており、第1回目に「アフリカの古民具展」、翌年はタイトルを変えて「Primitive Art 展」、そのほか全部で7回アフリカをテーマにし、中でもドゴンの柱と扉はそれぞれ1回づつ特集されている。中世キリスト教美術やデルフトの白い皿といった静謐なイメージのある後年の「古道具坂田」からは意外にも感じられるアフリカへの傾倒だ。「ひとりよがりのものさし」の連載においても、アフリカのモノは第1回のザイールの布に続いて今回のドゴンと2回連続、全体では9回採り上げられているが、第29回「アフリカの面」を最後に(エジプト美術に含まれるコプト裂は除いて)選ばれなくなったことは興味深い。
アフリカ、と聞くと今でも、裸の黒い肌に照り付ける強烈な太陽、ワニやヘビが潜む昼なお暗い密林、ゾウの群れが咆哮するサバンナ、という「暗黒大陸」のイメージが思い浮かぶが、それは西洋が勝手に投影した「未開・野蛮の地」のイメージであり、坂田さんもまたそうした植民地主義に毒されたアフリカ観を持っていたかもしれない。しかし美術館で、また仕入れに訪れたパリで、日本の平安仏や神像にも通じる白寂びたドゴンのモノ、力を秘めながらも穏やかに佇む縄文にも通じるアフリカのモノに出会うことでその先入観が打ち砕かれた。自らもアジアの片隅という「化外の地」にありながら知らず知らず刷り込まれていた西洋中心主義の視点で見ていたアフリカのモノに思いがけず日本のそれと同じ源流が流れていることを発見した、坂田さんはそこにこそ衝撃を感じ、また他の人にも同じ衝撃を感じて欲しいと思ったに違いない。だからこそ〈先輩の業者が「日本では”アフリカ”という名が付いたら美術品は絶対に売れないよ」と忠告してくれた通りであった〉(青柳恵介「骨董屋さんの主張」『別冊太陽 日本骨董紀行5』所収)にもかかわらずアフリカのテーマ展をやり続けたのではないだろうか。
「ひとりよがりのものさし」担当編集者であった菅野さんによると、今回採り上げられた柱と扉が現地でどのように使われているかを読者に伝えようとドゴンの集落の写真を掲載したが、そこに写っていた扉が装飾過多なモノだったことに坂田さんは抗議し、書籍化の際には外されたという。連載が始まったばかりのお互いに手探り状態だった頃らしいエピソードといえるが、ここには編集者サイドの考える、モノが実際に使用されることへの興味に対して、そこではない、という坂田さんの姿勢が明らかとなっており興味深い。
前回、ザイールとギーズベント、日本のボロ布の共通点は「用の美」かもしれないと書いたが、このエピソードから、坂田さんのモノの見方にとって「用」であるかどうかは必ずしも重要ではなさそうなことがわかる。屋号に古道具、と掲げているにもかかわらず、坂田さんの関心は「道具」にはなかったのだろうか? いや、答えを出すのはまだ早い。ここではっきりしているのは坂田さんにとってはドゴンであれば何でもいい、というわけではなかったということだ。
坂田さんが自らの先入観を打ち砕かれ、読者の先入観も打ち砕きたかったモノの例として挙げているのがこの「ドゴン族の柱と扉」で紹介されている「パリのミシェルさん」という業者が見出したモノだった。そして坂田さんが衝撃を受けたのはモノだけではなく、〈まだ誰も気づかない美しいものを探し出してくる(中略)それこそがアート・ディーラーの本来の仕事であり、価値の定まった品物を右から左に動かすのはただのブローカー〉と語るミシェルさんの姿勢だった。坂田さんはのちにミシェルさんのことを「自分の先生」(『芸術新潮』2009年4月号特集「パリと骨董」)と呼んでいる。
既成概念という自縄自縛を打ち壊すこと、誰もが普遍なものと信じて疑わない「美」とは、どこかの誰かが決めた権威に過ぎないのではないか、自分の眼と頭と心をもって、当たり前とされていることに安住するのではなく、もっと自由で広い世界があることを感じること。『ひとりよがりのものさし』全篇を通して、また「古道具坂田」や「美術館 as it is」を含む各所での展示において、つまり坂田さんが全人生をかけて表現しようとしたことはまさにそれだったし、ドゴンのモノとの出会い、パリの先輩業者の姿勢、から受けた二重の衝撃はその後の坂田さんを衝き動かし続ける原動力となったのだろう。
坂田さんは〈日本では戦国の時代、千利休が選択と取り合わせの絶妙な美を人々に提示した。あの時代、何が美しいかを明確にすることは死にもつながることだった。〉と続けている。
僕は千利休(や侘茶の創始者たち)、柳宗悦、坂田和實、という日本の美の概念を更新させてきた系譜(ちなみにこの取り合わせを僕は現『工芸青花』編集長が『芸術新潮』時代に提唱した「菅野史観」と呼んでいる。「菅野史観」についてはおいおい触れることになるだろう)を貫くものは「貧数寄」ではないか、と考えている。
日本が自らの宗主国である中華帝国一辺倒であった時代に珍重されていたモノはいわずとしれた唐物。ところが切った張ったにあけくれていた武士たちがようやく手にした点茶趣味は既に中国では流行おくれとなっており、抹茶茶碗への過熱する需要に対して供給は絶望的に不足。もはや新参者が這い入る隙もないほど確立された唐物マーケットに対抗するための新たな突破口を利休たちは朝鮮半島のモノである高麗物、そして新作である国焼に見出した。時は流れ日本のマーケットは利休らが打ち立てた茶道具一辺倒。名品は収まるところに収まりきっている。そこで柳宗悦が目を付けたのが朝鮮王朝の白磁、そして庶民の日用使いであった民窯や布。再び時は流れ柳らが称揚した李朝物や民藝の品々は高値の花に。正統な骨董マーケットからスピンアウトした坂田さんが見出したものが……という一連の流れは、富者が独占するマーケットと美の概念の既得権益に乗れなかった貧者が生き残りを賭けて放った起死回生のアイディアだったのではないか、というのが「美の更新=貧数寄」説である。
「いいものとは客がいいというものだ」という骨董業界の言葉があるそうだ。利休は生殺与奪の権を持つ「客」の価値観に歯向かって他の誰でもない、利休自身の「いいもの」を提示した。柳しかり、坂田さんしかり、「客がいいというもの」に逆らって自分がいいと思うモノを提示することは、切腹、弾圧、客が来なくて家賃が払えなくなる、の危険に直面しながらも、権威に対抗して只一人、おのれの道を切り開こうとする死に物狂いの表現だった。
ひとことに「美しい」という。それは誰の価値観なのか? 皆がいいというモノは、ただ誰かがいいというモノに過ぎないのではないか。利休も柳も、そして坂田さんも、自分の生を(経済的にも、そして本来の「生」の意味でも)生きるために、〈まだ誰も気づかない美しいものを探し出して〉こようとした。
彼らが〈探し出して〉きた〈まだ誰も気づかない美しいもの〉も気づかれた瞬間にたちまちマーケットの原理に組み込まれ、皆がいいというモノになっていく。しかし利休から柳に、柳から坂田さんに受け継がれていったものはモノではない。皆がいいということに流されず、生きるために、生きのびるために、美しいとは何かを自分の眼と頭と心で問い続ける姿勢なのだ。
〈一人一人が自分の責任で何が好きなのか、つまりはどんな道を歩きたいのか〉
僕たちは利休の、柳の、そして坂田さんのモノだけを受け継いではいないだろうか?

坂田室
東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)

