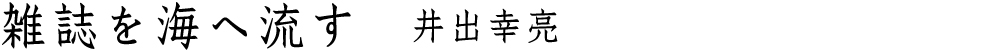
1 まえがき

2023年の秋、ふと思い立ち、自分が長年にわたって収集してきた古雑誌の表紙をiPhoneで撮影し、書誌情報を添えて、新規のInstagramアカウントを作成して(僕はこれまでSNSの類を使ったことがなかった)投稿し始めた。
・投稿する雑誌は、20世紀(1901-2000年)に日本で刊行されたものに限る
・いわゆる「商業誌」のみならず、同人誌、広報誌、ファンジン等も含む
・1日1冊の雑誌を投稿する
・1タイトルの投稿は1回のみ(つまり、同タイトルの雑誌を2度投稿しない)
・1年間(365日)、投稿を続ける
何が動機であったか、このいくつかのルールを自分に課し、毎日欠かさず投稿を続けた。仕事で遅く帰った日や疲れて何もしたくない夜も、何とか“任務”を完了させた。他者と共有するつもりはなく、ほんの数人の親しい人を除いてアカウントの存在を誰かに伝えることもなく(『工芸青花』の編集長・菅野さんはその一人だった)、ただ来る日も来る日も、「撮影→調査→執筆→投稿」という30分ほどかかる作業を黙々とこなし続けた。
過去四半世紀、僕が雑誌編集者として働いてきた期間は、このメディアにとって最も困難な時代だったと言える。言うまでもなくインターネットによる「情報革命」は、雑誌の社会的な役割を急速に侵食し、需要の減少を招いた。結果、雑誌というフォーマットは現在、世界のほとんどの国で消滅の危機に瀕している。この情報革命の本質が「広告革命」であったことを思えば、衰退は当然の帰結でしかない。しかし、現代の大半の人々はこの事実を気にかけることもないだろう。その姿は、絶滅危惧種の生物が誰にも気づかれずこの世界からひっそりと退場していく様子にも似る。
もちろん日本の状況も大きく異なることはないが、この国では雑誌が完全に消滅したわけではない。書店を訪れれば、棚に並ぶ雑誌の数の多さに驚かされ、いわゆる「雑誌不況」が大仰なプロパガンダに過ぎないのではないかと思うかもしれない。しかし、ひとたびそれらの雑誌の表紙をめくってみれば、そこに厳しい現実が浮かび上がる。売上減少と予算削減による効率化追求、ネット時代の加速度的な情報消費は、「時間もお金もかけられない」編集制作の状況を促し続けている。そして僕自身もまた、この状況の真っ只中で編集者として働いてきたのだ。
今から40年ほど前、当時の多くの人々と同じように情報に飢えていた小学生の僕は、週刊や月刊で発行される雑誌の発売日を心待ちにし、小遣いを握りしめて本屋へと走った。野球、アニメ、ロック、ファッション……そこには多様なテーマの雑誌が並んでいた。巧みなコピーライティング、かゆいところに手が届く詳細な情報、クスリと笑えるコラム、心躍らせる刺激的な写真やイラスト。高度経済成長後の「情報消費社会」の到来を経たこの時代、掲載された広告さえもが創造性に富んでいた。特に、雑誌の「顔」であり販売を左右する表紙は重要な存在であり、折々の時代を代表するようなアーティスト、イラストレーター、写真家、デザイナーによって入念に手掛けられていた。
雑誌はそのような才能豊かなクリエイターたちの最高の舞台であり、また僕にとって美しい喜びに満ちた夢の世界であり、また同時に「ここではないどこか」への扉でもあった。次号を待つ間、ページの隅々まで繰り返し読み耽った。この世界のどこかで、誰かが僕と同じ瞬間に同じページを読んでいると想像することに、不思議な興奮を覚えた。
大人になるにつれ、僕は少しずつ古い雑誌の収集を始めていった。アート、映画、音楽、文学、自動車、建築、料理、デザイン、スキー、瞑想、ホラー、プロレス、鉄道観察、将棋、アマチュア無線まで、古くは20世紀初頭まで遡る長い歴史の中にあらゆるジャンルを網羅する雑誌が存在した。これらの雑誌のすべてが、制作者と読者の情熱が詰め込まれた紙の砦であり、それぞれの時代の文化を克明に映し出す鏡のような存在だった。
そもそも大量生産品である雑誌は稀少価値が低く、あまりにも膨大な種類が存在するため、確立された価値体系はほとんどなく、古書店でも見つけ出すのは容易ではない。過去に発行された雑誌の正確な総数は不明であり、例えばレコードにおける「Discogs」のようなデータベースも存在しない。僕のコレクションもまた専ら個人的な興味関心に即して選び集めたものであり、体系的なアーカイブではない。
インスタグラムの写真撮影のため、長年本棚に眠っていた雑誌の1冊を取り出すたび、ページをめくる指が時間を忘れさせた。そこには驚くべき発見と瞠目させる表現、ヒントとなるメッセージが溢れるほどに詰め込まれていた。なぜこのような巨大な文化的遺産がまったく忘れ去られ、歴史の闇に埋もれたままであるのか。ほとんど義憤にも似た勝手な思いが沸き起こる。寂しかったのは、現在雑誌業界で働く人々でさえ、この素晴らしい歴史に対してリスペクトと関心をほとんど示さないという事実だった。
僕は夜ごと、それらを1冊ずつ拾い上げて埃を払い、インターネットという広大な海へと放流させていった。ごく親しい友人だけが時々、見守るように小さくコメントを残してくれた。どうしようもない高熱で寝込んだ2日間を除き、1年間かけて365冊の雑誌を投稿し終えた僕は、インスタグラムのタイトルを「365 Magazine Days:The graveyard where the Japanese magazines that flourished in the 20th century lie in peace.(20世紀に栄えた日本の雑誌が眠る墓地)」と名付けた。
これから始まるブログは、そんな奇妙な無償の行為の副産物として生まれたものだ。自身の雑誌コレクションの中から、気になる号を1冊ピックアップし、その内容を読み込んでみる。そこに立ち上がる風景がどんなものか、僕自身も楽しみだ。気軽にお付き合いいただければ本望である。

