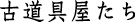
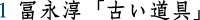

撮影|菅野康晴/工芸青花
京都市北区。2両編成のローカル鉄道・嵐電の等持院駅を降りて少し歩くと「古い道具」という名の、週に1日だけ開く古道具屋がある。店主の冨永淳(とみなが・じゅん)さんとは、これまで何度かお会いしているし同世代なのだけれど、生い立ちなどを聞く限り自分との共通点はあんまり感じられない。しかし、選んだものを気に入って私がニヤリと笑う時、決まって冨永さんも笑っているという光景に何度か出くわしたことがあって。そういうのは、嬉しい。だから今回、改めて話を聞くのが楽しみだった。冨永さんは、1978年生まれの42歳。美大を出て絵描きを志していたが、20代後半になって古いものに興味をもち、36歳のとき店を持った。店があるのは、住んでいる家の1階。玄関先のエノキの木が2階の高さまで伸び、午後には入口のガラス扉を通して店のなかにのんびりとした木漏れ日を作る。色あせた木製テーブルやブリキの小棚、時代箪笥の上に、アルミのやかんや湯のみ茶碗、飛行機のおもちゃ、紙の箱などが余白をもって配置されていて、経年でくすんだ色の重なりが心地いい。使い古した古道具なのに、ここで選ばれているものは洗いざらしたように清潔で、澄んだ空気に包まれているのはなぜだろう。冨永さん自身もスラっと長身で小綺麗で、生成りのセーターとチノパンがよく似合う人である。
─────
──冨永さんの興味が、美術から古いものに向かったきっかけは?
冨永 28歳の時、丹波の陶芸家・石井直人さんのうつわに出会い、生活道具に興味を持ったのが大きいと思います。石井さんは山を切り開いて住まいと仕事場を作り、自然と共存する凛とした暮らしのなかでものづくりをされています。うつわを家に持ち帰って使うと、そういうピンとした空気ごと感じられるような気がしました。それまでは、絵の具を溶いた皿を洗って食物をのせて食べても気にならないくらい無頓着な人間でしたけど、このとき初めて、いい空気を持つ生活道具ってあるんやなあと。勧められて骨董市に行ってみると、うつわや道具のことをあまり知らない僕でも、ものが持つ空気を頼りに自分の感覚で何かしら選ぶことができました。そういう世界があるのを知って嬉しかったです。
──古道具を購入するだけでなく、やがて売るようになりますね。
冨永 選ぶことが面白くなって毎週のように骨董市や道具市を見て買いまわっていると、家の中にモノがどんどん増えて。このままではマズイので「これはいつかお店を開くための」と口実にしたつもりが、本当にお店をはじめることに。石井さんの紹介で木工家の三谷龍二さんが(7割くらい完成していた)お店に来てくださり、三谷さんの運営するショップ「10cm」(長野県松本市)の蚤の市に誘っていただきました。これが「古い道具」のデビュー戦です。それがすごく楽しかった。
─────
三谷龍二さんとの縁は、2014年「松屋銀座デザインギャラリー1953」で三谷さんが監修した「7.5」展の出品へ繋がり、冨永さんはこれを機にお店を開く。和室だった1階部分をつぶして壁を白く、床をモルタルに塗り、ホワイトキューブのギャラリーのようなシンプルな「箱」を作ったのは、余計な装飾があると「ものの見え方が生ぬるくなる」気がしたから。この日、壁際の棚には、アルミ製にしてはずんぐりと丸く太った形の容器が3つ、おしくらまんじゅうするように隣り合って並べられていた。余白のある空間にそこだけぎゅっと密度のある景色。「おやっ?」と心をつかまれ、ニヤリと一息ついて「持ち帰るならこの周りの空気ごとでなくては」と思う。おそらく店主の目論見どおりだ。
─────
──ものの見え方が生ぬるくなるという意味は?
冨永 ものの輪郭や、ものとものの間の形なんかを見ています。例えばそこにある小さな折り畳みイスだったら、直線的な脚のエッジのきいた感じ、それに対してすこし外に広がっていく背もたれのふわっとした感じのコントラストとか。吹きガラスのものなんかは、白い壁の前に置くとキリッとした空気とふっくらとした輪郭がよくわかる。女性的なものの中にちょっと男性的なところがあるものとか、またその逆とか。そういうものに惹かれます。いわゆる骨董的な「ザ・男」というものは苦手です。
──意識して、素と密をちりばめた置き方を?
冨永 店のなかのあちこちで、そういうのをコソッとやるんです。まわりの空気も含めた全体をものとして見る癖があるから規則正しく置くことはあまりなくて、リズムでいったら、トン、トン、トトンとか、ちょっと外した感じになります。僕にしたら「すごくいいな」とニヤッとしながらやることですけど、お客さんにとっては気づくか気づかないかのことだと思います。ものを「選ぶ」のと同じくらい「並べる」のが好きだから、それに気づいてもらえた時は嬉しいですね。なにげなくものを置いた時の偶然の配置にドキッとすることも多くて、気持ちがハッと動いた間合いや空気感を覚えています。
──冨永さんにとって「並べる」とは、気持ちが動く間合いや空気感を目に見えるようにしていくことでもあると。
冨永 僕のリズムというのはありますね。自分の選んだものを自分のリズムで、もっと大きな空間、畳の部屋、モダンな家などに並べられたら楽しそう。並べるのと同じく、散らかり方にも好きな散らかり方と、嫌いな散らかり方があって。小学生の頃は、消しゴムはもう少し右上、カスは広げて、鉛筆は斜めにとかしていました。
──どんな子供時代でしたか?
冨永 絵が好きで、紙と鉛筆さえあれば静かにしているタイプでした。褒められたり、表彰されたりも何度かあります。その一方で、小−中学生時代は野球にも熱中しました。ピッチャーか三塁手。それこそ「ザ・男」という感じでしたね。高校では勉強を頑張っていて、一般的な大学に行くのだろうと思っていたんですが、「芸術系に進みたい」と言った幼なじみの発言が妙にかっこよく感じられて、僕も絵を描く学校に行くぞと単純に。大学では日本画を専攻したんですが、紙箱のウラや日に焼けたメモ帳とかに鉛筆で落書きのようなものを描いたりしていました。いまでも骨董市で日に焼けた紙や色のさめたり抜けているものには、目がいってしまいます。
──色のさめたものを選ぶのはなぜでしょう。
冨永 静かだからかな。ものとものの取り合せの中で古いものを見ているので強いものはしんどい。骨董市には色や形や素材の違うものが、これでもかとゴチャゴチャとあります。その中から、見過ごされ、気づかれていないものをすうーと拾い上げられたらと。
──まるで、ものに呼ばれるように?
冨永 むしろ見えすぎるのかなと思うほどです。「いいのがある!」と思って走っていったら、コーヒーの入った紙コップだったというのがよくあります。反対にプラスチックのカップだと思って通り過ぎようとしたら綺麗なガラスコップだったという時もある。こういう発見は楽しいです。
──プロダクトも手仕事も、どちらも選ぶ、選ばない?
冨永 プラスチックのような工業製品も手作りのものも分け隔てなく、ですね。ただ、同型の工業製品のやかんが10個揃っていたとして、そのなかで僕が好きなラインのものは1個しかなかったりします。好きなラインと好きな空気感を持つものでないと嫌ですね。作られた年代や誰が所有したか、どのように使われたものかなど、背景にはそれほど詳しくありません。扱うのはほとんどが日本製ですが、国籍もあまり意識していません。
──ではなぜ古道具を選ぶのだと思いますか?
冨永 古美術ではなく古道具は、出自を背負っていないのが面白いからです。背景が立派なものや、作った人の思いが強すぎるものはしんどくて。飛行機や積み木のような子供のおもちゃが好きなのも、ラインが単純だからです。背景を知らなくとも、誰もが思わず心動かされるであろうラインがいいなと。情報よりもののまわりに流れる空気に心を動かされてほしい。できれば僕さえもいなくて、ものだけ見てくれたらと思うほどなんです。
─────
冨永さんが「古道具」を扱いながら、その言葉を「古い」「道具」とかみ砕き、店名としていることも、情報を取り払う行為のひとつだろう。それは「古道具」というすでに世のなかにあるイメージから距離を取ることであり、その距離は、冨永さんがものを見る眼である。銘柄やウンチク、素材の特徴なんてどこ吹く風と、属性をとり払えば払うほど、その眼は輪郭やものがまとう空気にいっそう敏感になり、洗いたてのように誰も手をつけていないクリーンな線を選び取ることができる。
美大時代、日本画の代わりに、絵とも落書きとも言えない素描を描いたというが、冨永さんが古いもののなかに見つけるラインは、その鉛筆の線に近いのではないだろうか。美術を目指した学生が心を落ち着けることができる場所はここにあった。ここにいるのは、空間を線で満たす「古い道具」という名のひとりのアーティストなのだと思った。
(構成・文/衣奈彩子)




古い道具
京都府京都市北区等持院南町68-1
