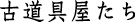


撮影|菅野康晴/工芸青花
「アポロギア」は東京から車で1時間半、千葉県長生郡長柄町の田畑が点在する場所にある。建物は使われなくなった米の貯蔵庫で、天井高は5メートル以上。コンクリートの外観に合わせてあつらえた鉄枠のガラス戸を開けて中に入ると、長さ2メートル以上ある大テーブルや、見上げるほど背の高い棚や木の扉、実物大くらいの木馬、流木や切株などの自然物、いくつもの大壺などがディスプレイされている。店主の田口雅啓(たぐち・まさひろ)さんは1983年青森県生れ。地元の大学卒業後、2006年に上京、アンティーク家具店で働いていた頃から、大きな家具、オブジェ的なものに惹かれていたという。独立して「アポロギア」をはじめたのは2017年。空間の構成要素としての古道具。写真が美しいインスタグラムを通じて、海外からの注文も多い。─────
──ここで扱うものは、どれもダイナミックですね。
田口 なぜか大きいものに惹かれます。店を開くにあたり、商品として想定したのは食卓の器物のような小物ではなく、インテリアの核となるような存在感を持つ古道具でした。家具以外では、農具のような民具が多いですが、餅つきの臼を逆さにしてテーブルにしたり、腰の高さほどもある壺をいくつも並べたりと、意外な見せかた、使いかたを提示するには大きな空間が必要でした。
──前職でも古物を扱っていたんですね。
田口 アンティーク家具や雑貨のショップを複数展開する東京の会社で、2010年から8年間、渋谷にある店のマネージャーを務めました。コンセプト作りや商品の仕入れ、スタッフの採用やオンラインショップの運営まで、すべてを手がけていました。そのころ感銘を受けたショップが碑文谷の Kousei Werkstatt(注・2000年開業。2015年「jipenquo」に改称)です。アンティーク家具の塗装を剥がし、白木の肌を活かす手法は、いまとなっては珍しくありませんが、Kousei Werkstatt がさきがけだった気がします。彼らによって和家具がファッションの世界に近づき、その背中に追いつきたいという思いで自分なりの表現を探求しました。ものと向き合ううちに、自分が、用途を失ったもの、作為を感じさせないものに惹かれていることに気づきました。
──どんなものでしょう?
田口 例えばこの、テーブルに見立てた臼などはそのころから扱っています。もともと市場でよく見かけるアイテムでしたが、天地を逆さにして置いてみると、ダイナミックなオブジェのように見えました。お客様の反応もよく、自分が発見したものが受け入れられたことにワクワクし、自信に繋がりました。それらのものの魅力を最大限に発揮させるために、空間に余白を作ることや、他のものとの調和を大切にしています。
──そもそも古物に興味を持ったきっかけは?
田口 きっかけはファッションでした。服が好きになったのは高校からです。十和田市生れで、地元の工業高校から、八戸の大学の建築科に進み、ひとり暮らしを始めました。インテリアに関心を持ったのはそのころです。服は古着が多く、通っていた古着屋の店主から「古物を扱う店がある」と聞いて訪ねました。1960-70年代の日本やアメリカの雑貨が主で、今思えば一つ一つはなんでもないものでしたが、僕にとってはすべてが宝物のように見えました。廃墟のような古い建物で、暗い店内に点在するそれらが輝いて見えたのです。そして、それを売っている、商いにしていることに衝撃を受け、自分も「これで生きてゆこう」と決意しました。
──それで東京に?
田口 そうです。すでに大学4年だったので、すぐに行動しなくてはと。古物業界を知るには、やはり東京だと思いました。首都圏のインテリアショップを紹介する本を買って、古物を扱う店のなかで、直感的にいいなと思ったところに電話をかけ、新卒で雇ってくれるかどうかを訊ねました。それで入ったのが前職の会社です。
──話は少し戻りますが、青森にいた高校、大学時代、ファッションやインテリアの情報はどこから?
田口 雑誌を読みあさっていました。中でも『FN(ファッションニュース)』は定期購読するほどでした。海外のコレクションの様子、ブランドの背景を知ることができる貴重な雑誌でした。大学の後半になるとやはりインターネットですね。各ブランドのウェブサイトを通じて、それぞれの世界観を知り、興味を抱くようになりました。
──ファッションのどこに惹かれたのですか。
田口 僕にとっては店の美意識、内装や、洋服をインスタレーション展示するような非日常感ですね。大学で建築デザインを専攻していたこともあり、そうした店からヒントを得ようともしていました。ブランドではアントニオ マラス(イタリア)やリックオウエンス(アメリカ)、アンダーカバー(日本)、コズミックワンダー(日本)に惹かれていました。いまでもよく思い出すのは、アントニオ マラスのアトリエの世界観です。廃墟をうまく使って、洋服と什器が調和し、退廃的な空気を生み出していました。
──いまは店よりもオンライン販売が隆盛ですね。
田口 店をやっている立場からいえば、できれば実物に触れて選んで欲しいという気持ちもあります。でも、ものの魅力をいかに伝えるかを真剣に考え、写真で世界観を伝えることも大切にしているので、ウェブでも共感してもらえると確信しています。僕自身、青森にいたころはウェブサイトを見て、オンラインで服を買っていた、買うしかなかったのですから。
──アポロギアの販売はオンラインが主ですか。
田口 はい。ほとんどがそうです。店を開けるのは月に2日ほど、ほかの日は仕入や、商品の仕上げ、撮影に充てています。昨年から、海外からの注文も増えてきました。
──「アポロギア」の近くには坂田和實さん(古道具坂田)の個人美術館 museum as it is がありますね。
田口 初めて as it is を訪ねたのは、渋谷でマネージャーを始めて数年経ったころです。窓際のコーヒーテーブルが臼を逆さにしたものだったことに驚いたと同時に、自分が歩んできた道が間違っていなかったんだとも思いました。as it is の近くに店を持つことになったことは偶然でした。
──古道具坂田のことは?
田口 2012年に松濤美術館で開催された「古道具、その行き先 坂田和實の40年」展で、初めて坂田さんの仕事を見ました。坂田さんの言葉を借りれば「ゴミ」のようなものがインスタレーション展示されていた。自分の店に置きたいと思うものを探して、よく観察し、その魅力を自分なりに解釈しようとしていました。そのあとで坂田さんの本を読むと、どの言葉もすっと胸に落ちる気がしました。後日、古道具坂田を訪ねたとき、いつか自分で店をやりたいと話したら、「絶対にやったほうがいい。苦しみも、だけど、喜びも倍になるから」と言ってくださった。とてもありがたい言葉でした。
──影響を受けましたか。
田口 坂田さんも、jipenquoの栗又さんもそうですが、尊敬する先輩たちは、それまで価値化されていなかったものに目を向けています。例えば鉄製のウナギ取りや、錆びたトタンを壁にかけて鑑賞対象にすることは、そうした先輩たちがすでに行なってきたことで、模倣といわれるかも知れませんが、僕としては、そうした価値観を受け継ぎたいという気持です。その上で、今度は自分が、これまで評価されたことのなかったものを拾い上げ、新しい方法で提案することができたらとも思っています。
──やりがいがありますね。
田口 市場などで評価されない、値段がつかないものの中に、自分にとって「光る」ものを見つけた時は気持ちが高揚します。そうしたものこそ、価値を高めてゆきたい。それができれば、これまで見捨てられていたものも、後世まで残ってゆきます。店名の「アポロギア」は、柳宗悦の『民藝とは何か』に記されていた言葉で、響きが印象に残りました。ギリシア語で「弁明」という意味ですが、僕としては、「ものをまっすぐに見る」ことと理解しています。「光る」ものはまだまだあります。
(構成・文/衣奈彩子)




アポロギア
千葉県長生郡長柄町徳増字川間315-2
https://www.apologia.jp/
