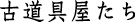
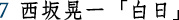

撮影|菅野康晴/工芸青花
「白日」のオープンは2016年。東京の下町の路地裏に残されていた築92年の蔵を利用した当時の店舗は、採光を最小限に抑えた蔵特有の造りを生かして小さな電球だけ灯し、暗闇に近い中でものを見る場所だった。仄暗い光のもとでは、朽ちたブリキの壁を背景に置く錆びた鉄板が前衛的なアートのように見え、古びた陶器の貫入や木皿の表情が深みを増して目に映った。ものが持つ陰影の美しさに気づかせるような展示は、20-40代の若い世代を中心にインテリアや雑貨に関心のある人々を魅了、古いものの世界に招き入れた。2018年、再開発のため移転した先も同じく下町の台東区柳橋。昭和初期の木造の建物は、かつて歯科医院で、ダークブラウンの重厚な木の扉が迎える。看板こそないが、1時間に数組の客が訪れ中に入っていく。その手にはスマートフォン。彼らのほとんどはSNSの投稿を頼りにこの扉にたどり着くのだ。店主の西坂晃一さんは1980年生れ。岡山で生まれ育ち、20代半ばまでは働きながら音楽活動、その後、上京し都内や埼玉の飲食店を転々と渡り歩き、36歳の時、古道具屋になった。─────
──なぜ飲食業から古道具屋に?
西坂 勤めていた飲食店では古陶磁器や作家にオリジナルで作ってもらったものなどで料理を提供していました。そこから器や道具に関心がわき、ある時から、本で知った西荻窪の「魯山」に通うようになりました。いつも見るだけで一言も話さず帰っていましたが、5回ほど訪ねた頃だったでしょうか。数千円の繭皿を1枚買ったんです。すると店主の大嶌さんに初めて声をかけられました。「お前、時々来るな、まあ座れ。仕事はなんだ?」と聞かれたので、飲食をやっていると言うと「突き抜けろよ。この世界、突き抜けなきゃ意味がないからな」と。衝撃的でしたが、ストレートな言葉は心に響きました。そんな大人は周りにいなかったので。 それからですね。飲食を続けながら古物商の許可を取り、古いものを仕入れて、月に1回、自宅を開放して売るようになりました。琺瑯の食器や子供用の椅子など、比較的分かりやすいものです。その頃の自分は宙ぶらりんで、どっちつかず。古いものを売りたいというより、変わるきっかけを探していたのかもしれません。大嶌さんの言う「突き抜ける」ための何かが、自分で見つけ出したものを人に伝えることにあるような気がしていたのだと思います。
──古道具に初めて触れた時の感覚を覚えていますか。
西坂 古いものを見て「これいい」と感じる感覚は、とても純粋なものでした。自分はそれまで同じ仕事を長く続けた経験があまりなかったのですが、古道具の買い付けだけは続けられました。どんなに疲れていても「まだ見たことのないものが見たい」「仕入れにいかなくては気が済まない」という初期衝動がいつまでも消えませんでした。2014年に料理人の道はきっぱりと諦め、ヤフーオークションやフリーマーケットでの古物販売を経て、2016年に「白日」を始めました。
──なぜ古道具屋は続いたのでしょう?
西坂 続いたと言ってもまだほんの数年ですが。小さい頃から筋の通らないことが嫌いでした。大人が悪気なくうやむやにしてしまうことや、物事を上手く進めるために用いる言葉に敏感に反応して、その裏側にある本当のことに気がついてしまうような子供でした。仕事でも上司の言葉や言動を見極めて、辻褄の合わないことがあったり、商売上のカラクリが見えてしまうと黙っていられず、良好な関係を続けられなくなるんです。要は大人の事情を解せぬ子供だったのでしょう。しかし古物は違いました。歩いて見つけ出してきた古物と自分のあいだには混じり気がない。だから続いたのだと思います。ただ、その魅力を多くの人々に伝えることは本当に難しく、音楽活動をしていた時の感覚にも似ていました。
──音楽活動とは?
西坂 高校3年の頃、友人の影響でヒップホップを聴き始めました。何事も自分でやらなくては気が済まない性分で、卒業する頃にはリリック(歌詞)を書くようになりました。90年代後半、その業界の賑わいは東京に一極集中。しかし、地方であってもその土地その土地を統治している大御所はいて、何度も曲を作っては自ら売り込みました。ようやく、人もまばらな明け方、みかん箱のような簡素なステージで酔っ払い相手にマイクを握らせてもらえるようになりました。その後は人脈を築いてステージに上げてもらうよりも、自分でライブイベントを主催するようになりました。その方が生きた心地がしました。初めて赤字を脱して、ほんのわずかなあがりを握って、皆んなで食べたファミレスのハンバーグの味は、その後の僕の人生の礎となっています。ヒップホップは、生きていく中で起こりうる、良いことにも、悪いことにも、自分の弱さとも真っ直ぐに向き合って、感情をさらけ出し、音にのせてメッセージを伝える音楽です。キレイごとだけじゃない。それが「キレイということ」なんだと思います。
──商売でもそうですか?
西坂 商売上においても徹底して意識しているのは、今も影響を受け続けている北海道を拠点とするヒップホップグループ「THA BLUE HERB」の、コントロールされずに全てを自分たちで決めて舵をとっていくインディペンデントなスタンスです。うちでは現代作家の作品も扱っていて、作品の魅力と同じくらい作家の人間味も重要だと考え、SNSを使って写真と言葉を尽くして紹介するのですが、作家の暮らしや懐事情、意見の食い違いも、わだかまりも、そのあとに訪れる喜びも、ありのままを綴っています。展示会の売れ行きは、作家の生活に関わりますからシビアです。どちらか一方が引っ張る関係性ではなく、作家も店も一丸となって結果を出し続ける店でありたい。インスタグラムを見て訪ねてくれるお客さんが多いのですが、SNSの良さは、自分の言葉で、嬉しいことも、納得のいかないことも伝えられることです。その言葉に共感し、家族のような強い信頼感を抱いて来てくれる人もいます。商売のリアルな話を公開する店は多くないと思いますが、日々の正直な言葉の積み重ねは、一過性ではなく、長いあいだ、店に興味を持ち続けてくれるきっかけになるのだと感じています。
──古い建物を選んで店を構える理由は?
西坂 古い建物を残すことも古道具屋の仕事だと思うからです。建物がひとつ残れば、古い街並みが残る可能性も高まるはずです。前の店舗は築92年、いまは築94年。東京では希少な昭和初期の建物を歩いて歩いて探しました。店に足を踏み入れて、古い建物を格好いいと感じる人がいるならば、いつか、世の中全体の建築、景観に対する意識まで変えることができるかもしれない。古いものを扱う者として、真新しさばかりが際立つ、のっぺりと似たような顔をした街並みが増えていく現実に抗いたいんです。
──西坂さん自身が好きなものは?
西坂 人工物が自然に還っていく途中にあるものが好きです。朽ちた板や鉄クズのようなものをとても美しいと思います。自然物では削られて角の取れた石や倒木から剥がれ落ちた樹皮など。子供の頃はよくものを拾って持ち帰っていました。育った場所が備前に近く、川底には綺麗な陶片がいくつもあり、集めていました。
──鉄クズを部屋に置きたいという感覚はお店のディスプレイに通じますね。鉄クズも古道具?
西坂 自分が古道具として最も美しいと捉えているのは、ボロや朽ち果てたもの、過酷な環境や貧しさの中で頭と手を使って工夫してつくり出した、手沢の残る暮らしに必要な道具たちです。「ない」なら作る。その考え方に価値があると思います。使い道のない錆びた鉄クズも、ほどよく手を加えることで輝き始めます。店にはものをたくさん置きたいですね。陶器も木の皿や箱も鉄板もガラス器も、あらゆる素材の、国も時代も違うものが雑多にあるのに、空間の中で調和している状態が好きです。ディスプレイは頻繁に変えます。繰り返し店に来てもらうのは簡単なことではないので、いつ来ても楽しんでもらえるように。お客さんは、実はものより、店を選んでくれていると思うんです。これまで価値がなかったものでも、自分が選び、ここに並べることで、評価され、残っていくことを願っています。
──「白日」の店名の由来は?
西坂 隠れているモノや人を「陽の当たる場所、表舞台に出したい」という強い気持ちをもってつけました。独自の世界観を持ち、人を惹きつける力のある象徴的なアーティストがひとりいることで、そのジャンル全体が盛り上がり、評価を受けることがありますよね。特にヒップホップは土着的な側面があり地域ごとに文化が違い、そのアーティストが活動している街ごとリスペクトの対象になることもある。影響力のあるミュージシャンが、リスナーはもちろん、それに関わるたくさんの人を幸せにするように、白日も人を惹きつける力を高めて、古いものを格好いいと思う人、それを暮らしに取り入れたいと思う人の“数”を増やしていきたい。知られていないモノや人はまだまだたくさん存在すると思います。自分はそれを見つけ出し、新たな価値をつけていくために、感覚を信じて強く立っていたい。小さくとも意志のあるひとりが存在することが大事です。
(構成・文/衣奈彩子)



白日
https://www.instagram.com/hakujitu_/
