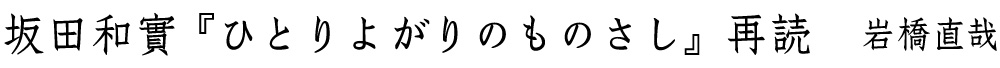
3 平瓦

『ひとりよがりのものさし』を再読してみてあらためて感じたことのひとつに、その軽妙な文章のそこかしこに顔をのぞかせる坂田さんの屈託、があった。「古道具坂田」を訪れたことのある人なら誰しも、坂田さんの穏やかな微笑と話しぶりを懐かしく思い出せるのではないだろうか。しかし坂田さんがふと見せる厳しい表情に驚かれされた人もまた少なくないと思う。
あるとき、「古道具坂田」に行く途中にあった蕎麦屋が居心地良くて好き、という話をしたらさっと坂田さんの表情が冷たくなり、あの店はなんとかいう有名な店で修業した人がやっているがそれほどではない、とこんこんと諭され、阿佐ヶ谷にあるお店を推薦されたことがある。いや軽い話題のつもりが、と鼻白むほどだった。
「ひとりよがりのものさし」担当編集者だった菅野さんからも坂田さんは強いこだわりを持った人だった、と伺った。例えば新幹線に乗るときは必ず自由席でなければならなかったそうだ。移動は夜行バスの僕からしたら大差ないように見えるが、坂田さんにとってそれは譲れない一線だったらしい。坂田さんの普段の柔らかな物腰の奥には強い屈託が隠されていたようだ。
『ひとりよがりのものさし』の文体はカタカナ表記が多用された諧謔に満ちたもので、それはどこか昭和軽薄体を思わせる。三波春夫や八代亜紀に加川良といった演歌やフォークソングがちりばめられた語り口からは、ヒッピーやボヘミアンが移り住み、風呂無し四畳半に下駄履きの貧乏でも自由な生活を標榜していた昭和40年代頃の東京の中央線沿線文化のイメージが浮かび上がってくる。奇妙に感じられるのは、この連載が書かれていたのは1999年から2003年にかけての、平成日本が未だバブルの遺産である消費文化にどっぷり浸かっていた、中央線的価値観とは真逆の時代であったことだ。その時代にこのいささか時代遅れな文体は、バブルへの反省も将来への知見もないまま、漫然と豊かさを貪り続ける当時の世相への異議申し立てとして意図的に選ばれていたと言う見方はできないだろうか。では果たして三波春夫や八代亜紀といった昭和40年代的感性を坂田さんはどう捉えていたのだろう?
明治以降西欧列強の真似をして植民地獲得競争に邁進していた日本「帝国」が戦争に敗北したその年、昭和20年に生まれた坂田さんの人生は、戦後民主主義国家としてよちよち歩きを始めた日本とその歩みを同じくしているが、昭和40年代は日本においても坂田さんにおいても人生の花である青年時代にあたったはずだ。しかし日本と同じく坂田さんのそれもなかなか一筋縄ではいかなかった。
〈坂田さんはインタビュウなどで、自身を「ふつうの子どもだった」と語っている。〉
と菅野康晴『生活工芸と古道具坂田』所収の「坂田さんの仕事」にある(以下の坂田さんの人生の軌跡も同書の記述に準じている)が、僕には坂田さんが大学で選んだのが文学や哲学まして美術でもない経済学部で、入ったサークルが広告研究会だった、というのがあまりに<ふつう>で意外だった。しかし卒業後入社した一般商社(これまた〈ふつう〉!)を坂田さんは2年で退職してしまう。
〈会社をやめたとき、坂田さんは「人生を捨ててしまった気がした」そうだ〉(同)
退社後坂田さんはヨーロッパを3か月放浪、その後1年間をイギリスで皿洗いや掃除夫をして過ごしたという。パリ5月革命に象徴されるカウンターカルチャーの世界的盛り上がりのさなか、経済学部(よもやマルクス経済学ではないだろう)と広告研究会を経て商社に進み、結果的に70年安保をスキップすることになった坂田さんはあまりにも〈ふつう〉なノンポリ青年のようで、当時の反権威的な若者のマインドとしては〈ふつう〉ではなかった。しかしせっかく入った商社をドロップアウトしてのヨーロッパでの放浪生活は、当時のユースカルチャーとしては〈ふつう〉であっても高度経済成長時代を担わんとする日本の若者としては<ふつう>ではなかった。相反する価値観の中で坂田さんはもがいていた。
1971年に帰国後は青山の一流古美術店の店員として働くというもうひとつの〈ふつう〉の道を目指すも1年で辞めてしまう。
大学を出て企業に就職、という〈ふつう〉からのドロップアウト、古美術店で修業して独立、という〈ふつう〉からのドロップアウト、というふたつの挫折。しかしその間には誰にも頼れなかった、何にも頼らなかった独りだけのヨーロッパ生活があった。
〈現地の若者たちと出会い、彼らのまえむきな考えにふれることで、人生すてたもんじゃない、と思うようになっていった。このあと日本に帰国しても、なにをやっても生きていける、という自信がいつのまにかついていた。〉(同)
『ひとりよがりのものさし』の四畳半的文体は、バブル後の平成日本の〈ふつう〉を撃つものとして意識的に選ばれている。しかし三波春夫の万博音頭や八代亜紀の情念に満ちた演歌、またフォークソングさえも、坂田さんがそこからドロップアウトした昭和日本の〈ふつう〉であったはずだ。それらは単純な青春へのノスタルジアではなく一種のメタ的なパロディとして採用されており、それによって連載当時の日本の〈ふつう〉と、そこに連なる過去の日本の〈ふつう〉のふたつを同時に否定するという韜晦と屈折に満ちたものなのだ。もっといえば否定されているのはそうした〈ふつう〉に安住しようとし、そして出来なかった坂田さん自身なのだと思う。
たかが蕎麦屋の話題ひとつに表情を変えた坂田さんを思い出し、その厳しいまでのこだわりを思う。坂田さんのこだわりとは、僕にとってモノへのそれというより、ものごとへの自分自身の向き合い方に、であったように思えるのだ。それはふたつの〈ふつう〉に挫折し、そのはざまの細い道を独り往く自分が、いかなる〈ふつう〉にも傾かないために自分を戒める厳しさだったのかもしれない。
そして1973年、オイルショックのどん底からバブルの狂騒へとむかう右肩上がりの時代に坂田さんは、拾った椅子を200円で売る〈ふつう〉ではない店を立ち上げることになる。
……今回このような前置きから始めたのは、例外的にこの「平瓦」の回はそうした韜晦や屈折のない、幸せなノスタルジアに満ちたもののように感じられたからである。見てみよう。
日本の奈良時代の瓦が紹介されている。それも文様などの特徴がある軒瓦ではなく平瓦。ただわずかに湾曲した四角い、焼かれた土の板である。軒瓦などはその文様によって使用された時代や寺院が特定されるため骨董マーケットで相応の地位を占めているが、
〈有難いことに、無釉の武骨な平瓦は長い間見過ごされ無視され続けてきた。〉
軒瓦であれ平瓦であれかつては同じ大伽藍の屋根を葺き、長い歳月をくぐってきたことには変わりない筈なのだが、文様という余分な情報がないことによって平瓦は学術的・骨董的価値が認められない代わりに、ずっしりとした土の塊の量感、窯の中で炎に舐められてできた複雑な色のグラデーション、風雨に晒され時に火中してざらざらと複雑さを増した手触りといった、よりモノそのものの素材感・存在感が純化されている、と坂田さんは考えているようだ。
次に紹介されるのはソウルで仕入れた18世紀の朝鮮王朝時代の平瓦である。海を隔てて同じルーツを持つモノ同士の、数百年の時を越えた出会い。
〈大きさは不揃いで、厚さもまちまちなのはいかにも李朝のものらしいが、手にズシリとくる重さ、おおらかなフォルムはたしかに先祖の姿。〉
モノとして純化した平瓦の佇まい、それが時代と場所を超えて共有されているということ。時空やモノに付加された意味を超えて共通するフォルムと質感という見立ては、やがて平安の経筒と昭和のブリキ缶を並列して視る透徹した視線へと繋がっていくのだろうけれど、奈良時代の平瓦と朝鮮王朝時代のそれを比較する坂田さんのまなざしはここではどこか夕焼けを見るような優しげな懐かしさに満ちている。
〈瓦の製法は飛鳥時代に朝鮮から瓦博士がやってきて日本人に教えてくれた。その後、日本の瓦づくりはずいぶん進歩したけれど、教えてくれた先生の国ではずっと古代の製法を守り続けたらしい。〉
文様がないただの土の板であるゆえに冷たい学術的分類や金額の多寡で計られる骨董ヒエラルキーでの位置づけをまぬがれた半島と列島のモノを、そこに通底するモノとしての確かな素材感・存在感を通して拾い上げることによって、同じ祖先を持つ両者を千年の時を超えて出会わせることができたことを坂田さんは喜んでいる。
磁器よりも陶器、陶器よりも土器に懐かしさを感じるのは何故だろう?ぴかぴかと光り輝くモノよりもざらざらと脆いモノに安心するのは何故だろう? 我々の記憶もまた、ざらざらと粗い、脆く儚げなものだからなのだろうか。
坂田さんが千葉に建てた美術館「as it is」に並べられた数十枚の朝鮮王朝の平瓦には、四角いフォーマットの連続というミニマルな、しかしそれぞれの不揃いな細部と豊かなグラデーションのある色合いが織りなすポリフォニックなリズム、いわば不連続の連続とも言うべきという現代アート的な文脈が坂田さんの眼には備わっていることを示している。
しかしソウルの道具屋のお母さんからの、〈まだ屋根の上〉に乗っている空色の瓦を買わないか、という電話には、その人間味あふれる誤解? には感謝しつつ、買うことはなかったと坂田さんは文章を結んでいる。つるっと光り輝く〈きれいな色〉の瓦にも現代アート的なリズムはあるだろう。しかし今回坂田さんが朝鮮王朝の土の平瓦に感じたものは、坂田さんのなつかしさとは、奈良時代と朝鮮王朝時代の瓦と、ソウルのお母さんから「サカナさん」への電話に共通する、海を越えたモノとヒトとのあたたかな交流の歴史を、そのざらざらとした手触りに感じることだったのだろう。

坂田室
東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)

