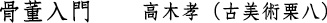


「真贋の森」の表題は、松本清張の小説にあるタイトルで、贋作作りのお話です。かつて実際におこった春峯庵や佐野乾山、永仁の壺事件等を下敷きにして、学会、マスコミをも巻き込んだ顚末を描いています。新潮文庫では『黒地の絵 傑作短編集(二)』に収録されています。興味のある方は御一読ください。
■信楽自然釉大壺
これは私が骨董屋となって数年を経た頃の出来事です。当時は郷里新潟への仕入れは車で、開通したばかりの関越自動車道を使っていました。新潟市内から東京(練馬)まで片道約3時間、休憩をせずとも戻れる移動距離です。気が向けば高速を途中で降り、周辺の骨董屋へも時々は立ち寄っていました。新潟での仕入れが充足した時は資金も使い切り、立ち寄る余裕もないのですが、あまり収穫がなく、手もとの資金にも余裕のある時は、「何かありそう(買えそう)」と思える関東の店の数件を訪ねて廻っていました。たいがいの場合、「買えない時は買えない」もので、数軒を廻っても目ぼしい品には出会えず空振りとなる途中下車が多かったものです。
その日も、「何か……」と期待した数軒では何も買えず、まだ時間の余裕があったので、刀剣や武具を専門とする店主なのですが、かつては関東より見出された仏教美術や時代工芸も店先に並べていたお店へと行ってみることにしました。
久しぶりに訪ねてみると、関東の小京都と云われ、観光客誘致に熱心だった町並みはすっかり様変わりし、以前なら店頭に車を停めておけた道路は取り締まりが厳しいと云うことで、近くの駐車場へ車を置いてくることになりました。駐車場に車を留め、件の店へと向かう途中、「〇〇古美術」と書かれた小さな看板のある家があります。前には無かったか、車で通過して気がつかなかった店です。気にはなったのですが、店主が待っている件の店へと向かいました。
「やはり」と云うべきでしょう、店には目ぼしい品はなく、昔話をしばらくし、「そう云えば……」と途中にあったお店のことを尋ねてみました。「あー、あそこはね」と店主、蒐集家だった主が定年を機に家の一部を改装して、数ヶ月ほど前に始めた店で、あなたが行っても買うものはないだろうと云う話でした。
が、私はもう行く気満々です。件の店をあとにして、あの小さな看板のお店へと向かいました。玄関で来意を告げると、「どうぞ……」と居間を改造した店内へと招いてくれました。まだ客の相手には慣れぬ様子の店主でしたが、無遠慮に店(居間)に置かれた品を見て廻ります。飾られている品は、値に陰りの見え始めていた古伊万里が中心で、確かに買いたい(商いになる)と思える品がありません。
居間と掃き出しの間に小さな板の間があり、隅に大壺が一個置かれていました。カーテン越しの陽をうけて肩の自然釉が鈍く光って見えます。姿や口造りから中世の信楽大壺であることは遠目にも分かります。手にも取らず、「あの壺はいくらですか?」と顎で指して尋ねました。「25万円です」と、遠慮がちな店主の応え。では、と近づき手に持ち、疵や共直しのないことを確かめ、「買います」と私。50センチ近い、自然釉の残る室町時代の信楽大壺が、バブルのはじけた後とは云え、25万円とは市場値の3分の1程です。「車ですからそのままで……」と支払いを済ませ、壺の口に手を掛け抱えて持ち帰ってきました。
買ってきた後、しばらくは床の間に自慢気に据えていたのですが、いつも来る知人や業者が誰ひとりとして大壺に触れません(話題にものぼりません)。古窯好きの数名も眺めるだけで、触れもせず、値段も訊きません。値を訊かれたなら掘り出し話と共に幾ばくかの利を乗せて、との心づもりでいた私も拍子抜けです。
1週間ほどして、肩にかかる自然釉の鈍い艶が気になりだしました。裏返せば下駄底の跡もわざとらしさが目立ちます。壺の中を覗いて贋作(今出来の壺)と確信しました。使われてきた痕跡がありません。数年前に骨董屋になった、経験も知識もない私が、開業したばかりときいて店主を見くびり、「掘り出し」と勝手に思い込み買ってきた信楽大壺の正体がこれです。
■後日談
いかがでしたか。長くなりましたが、私の慢心が招いた失敗談です。件の「信楽大壺」は、自分のやっていた会ではとても処分する気にはなれず、当時、古窯のよく出る市場として定評のあった、青山のいけだ古美術さんが会主をやられていた会へと持ち込みました。結果は、ひとりの業者の「50万円!」のひと声で決まりました(売れました)。
市場で、どうしても欲しい品の出た時、会主の発句(最初の競り値)を待たずに、買いたい値を告げる、「跳ぶ」と云う競り方があります。高値で跳ばれたら、同様に欲しい人は更に高値を告げるしかありません。「50万円」と跳ばれた競り声に、例えば「52万円」などと細かく競り上らないのが暗黙のルールなのです。古窯に詳しい業者も多く集まる会です。私は何だか悪事を働いた者と見られている気がして、居たたまれぬ気持ちで後の会に参加していました。
会の日の夜です。青山のいけださんから電話がありました。「高木さんねー、最近良くできた信楽がうちの店に持ち込まれているから、そちらも注意して……」との話です。昼間の大壺についてはひと言も触れず、それだけ言うと「じゃあ」と電話は切れました。いけださんから骨董品についての電話があったのは、あの時一回きりです。
■最後に
「真贋の森」で、私の経験した三つのことがらについて書かせていただきました。私の奢りと慢心が招いた結果ですが、私自身は失敗の過程で、心ある先輩に大きく助けられました。今でもありがたく感じ、心に残る出来事となっています。
「これ以外には贋作を仕入れたことはないのか?」と問われれば、「とんでもない」と応えます。まだまだ失敗談は現在進行形で続くのですが、私の「真贋の森」はひとまず終了です。
次回は、「真贋の森」で迷わぬための骨董蒐集について書かせていただきます。ようやく、役立ちそうなブログになりそうですね(笑)。
馬板 江戸時代 11×15cm
─
「馬板(うまいた)」と呼ばれている長さ10センチほどの小さな版木で、可愛い馬が彫られています。表裏は墨と煤で真っ黒、時を経た枯れ具合には独特の風格と味わいがあります。かつて新潟から群馬にかけての山間地の古い民家より、煤けた道具や陶磁器、家具等と共に、買い出し屋さんが時折り仕入れてきたものです。「何で新潟の山の中に小絵馬の様な版木が……」と不思議に思いながらも、可愛いので見つけたら仕入れていました。
今から10数年前、民具や籠、敷板、民間仏、やきもの等を、年に一度(七夕の頃)、青山で「古民藝展」と云う展示会を開いて販売しており、仕入れてきた馬板の数点も毎回展示していました。「古民藝展」に開場前から並ばれる熱心なお客さまがおり、その中のお一人が、あとで知った事ですが、馬板や獅子頭等、山間地に伝わった民間信仰品の熱心な蒐集家である岸和雄さんでした。岸さんから、越後の山間地に馬板の残されてきた背景を伺うことができ、翌年の古民藝展の小冊子には「馬板(取材ノートから)」の一文を寄稿していただき、有意義な1冊として発刊することができたのも懐かしい想い出です。
「古民藝展」の頃には、年に数点は仕入れることのできた馬板ですが、今ではすっかり見かけなくなっていました。先日久しぶりに、郷里の古くからの馴染みの同業が東京の市場へ売り物にきて、その中に籠や民具と共に馬板がありました。骨董としては一般的ではなく、粗末で素朴な馬板ですが、意外とライバルも多く、何とか競り落とすことができました。安い買値ではなかったのですが、古民藝の魅力が若い同業や蒐集家にもしっかりと根付いている様でうれしい気持ちになりました。

*骨董通販サイト seikanet はこちらから
https://store.kogei-seika.jp/

