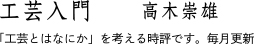
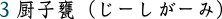

なんとなく今回も沖縄のこととなりました。
厨子甕(じーしがーみ)をご存知でしょうか。かつて、奄美諸島から八重山諸島にわたる琉球弧と呼ばれる地域においては、亡くなった人を墓室内に安置して風葬し、数年後に墓開き(じょーあきー)して骨を洗う、という風習がありました。厨子甕は、洗った骨を納める為の、いわば骨壺です。
かつて、というのは正しくありません。そのことを僕が知ったのは、2015年に沖縄県立美術館・博物館で行われた「琉球弧の葬墓制」という企画展でのことです。出張の折にふとチラシを見て、何の気なしに行ったら、会場を出る頃には、……このたびはまことに……といった気持ちとなり、すっかり参ってしまいました。さすがに今は火葬だし、洗骨はしてないだろうと思っていたら、いやいやしっかりと、紙パック入りの泡盛を振りかけて、遺された人たちが焼かれたあとの骨を洗う地域がまだあるのですね。その一部始終を写した映像を見て、死者と生者が同じ時間を共にする土地の強さに感じ入ったものです。実に見事な企画展でした。
そんなわけで、厨子甕はいわゆる骨壺よりも多くの骨を納めないとならないため、しっかりした大きさを持つものが多く、形も素材も様々です。初期は木や岩で作られているもの、珊瑚から生じた石灰岩を用いたものなどが主でしたが、17世紀後半以降は陶器で作られているものが増え、特に18世紀頃から作られた御殿(うどぅん)型と呼ばれる厨子甕は、まるで竜宮のようで、どれも立派です。益子参考館に行けば、濱田庄司が蒐めた古い御殿型の厨子甕が庭先にぽんと置かれていたりして、いや、すごいものだ、こんなにすごいものが当たり前な時代があった、なんでこんなところに置かれているかは知らないけれど、とつくづく感服します。
ただ、僕はああいう立派なタイプの厨子甕は欲しいと思えない。あっても置く場所ないし。そんなわけで、手元にあるのは、照屋佳信という方が作った、ごく小さなもの。褒めちぎるほどのものではないし、悪いものでももちろんない。書架の片隅に置いて、自分と家族の遺灰を入れる予定にしています。友人が石垣島で撮った御嶽にも似て、僕らもいずれここへ行けるのだろうか、と安心を覚えます。しかも、ひとつ手に入れたから、これで十分。シェイクスピアの言う通り、人間は一度だけ死ねるのだから、厨子甕は数が要るものではない。それも好ましい。
ちなみに、沖縄では今もやちむん(焼きもの)を作る人が、それなりに厨子甕も手掛けるので、探すのはそう難しくありません。金城次郎や大嶺實清、上江洲茂生、ほか幾人、亡くなった方も生きている方も、みなさんそれぞれに良い厨子甕を作りますし、そもそも、悪い厨子甕っていうものを見かけたこと自体、ほとんどない。不思議と、やちむん全般には、老いをおそれることのない強さがあるようで、日々しっかりと働いてくれて、長い間にだんだんとくたびれてはくるけれど、その古びた静かなたたずまいも心地よい。遺された厨子甕はその最たるものです。
*続きは以下より御購読ください(ここまでで記事全体の約半分です)
https://shop.kogei-seika.jp/products/detail.php?product_id=342


