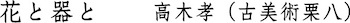
22 陶筒残欠

冬の間、屋上の草木の多くは枯れてしまい、古びたプランターだけが並ぶ殺風景な景色になりますが、夏の茂りとは別の趣があり、嫌いではありせん。福井に住まわれたアンフォルメルの画家、小野忠弘氏はかつて、自身が見出した能登の黒陶(珠洲壺)を「寂漠人間の終息物」と表現していました。枯野に晒された壺がイメージされ、好きな言葉でした。
屋上の枯野から紫蘭の枯れ枝を抜きとり、赤錆びた陶の残欠に挿してみました。骨董屋なのですが、この陶筒がいつの時代の、どこの焼きものかを知りません。若い頃、小野先生に出会い励まされた絵は、中途半端なままで描ききれませんでしたが、これで良かったと今は思っています。

日本映画学校のこと 今村昌平さん その1
デザイナーとして東急エージェンシーに勤めていた頃のことです。青年座の仕事も定期的に続けており、その縁から、今村昌平が開設していた私塾の仕事を頼まれました。アルバイトです。私塾は横浜放送映画専門学院と云い、映像(映画)界で活躍できる人材を育てるために、今村昌平が私費を投じて開設していた学校です。横浜駅に隣接する古いビルの一角で、教室をひらいていました。
依頼された仕事は、学院の発行する脚本集のデザインでした。小部数の機関誌と云うことで、軽い気持ちで引き受けましたが、これが揉めました。以前に発刊されていた脚本集を見せてもらうと、カットや表紙のデザインが時代遅れの同人誌と云った体裁で、なんとも安っぽい印象です。収められている脚本は生徒の卒業記念創作集なのだと聞かされ、「この体裁では……」と哀れにさえ感じました。
思ったことを口にして生きてきた私ですので、「こんな冊子をもらっても、学生は親や友達に自慢して見せられないだろう」と、編集担当の講師に意見してしまいました。すると「本(脚本集)は中身だ」と反論されました。「なら、何で俺に頼む」と言い返すと、「俺は頼んだ覚えがない」との返事です。「なら、帰る」と席を立って帰ってきました。
頼んだ覚えのない脚本集の担当講師は馬場当氏、今村昌平映画の多くの脚本を共同執筆する著名な脚本家でしたが、もちろんそんなことは知りませんでしたし、知っていても同じことを言っていたでしょう。
それから数ヶ月経った頃、再び学院から連絡があり、相談したいことがあるので来て欲しいとのことです。「あそこはどうなっているんだ」と云うのが私の思いでしたが、先に大人気ない対応をしてしまった後悔もあり、お詫びをかねて出かけて行きました。
これが、今村昌平の学院(後の日本映画学校)との長い付き合いの始まりとなりました。
https://store.kogei-seika.jp/

