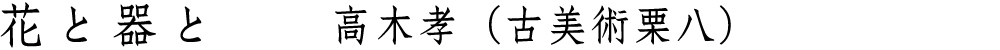
80 時代竹籠

よく使い込まれた時代の竹籠で、金具が付き掛花入に見立てられています。有名な竹籠花入に、利休が桂川の漁師から魚籠を譲ってもらい花入れにしたと伝わる「桂川籠」があります。“花は野にあるように、一色か二色かろがろと生けたるがよし”と利休は茶花の秘訣を伝えたと云われています。私の花は素人ですが、“一色か二色の花を、野原(屋上)から手折り、そのまま軽やかに生ける”ことができたなら上出来と思っています。花は山吹と駒繋(コマツナギ)です。

村山さんのこと その3
村山さんに「これを」と言われ、買ってきた小皿は調べてみると、どうやら古染付(コソメツケ)と云うのだと分かりました。「古染付芙蓉手深皿」、薄作で呉須の濃い磁肌の美しい皿でしたが、20歳になったばかり、骨董に触れ始めたばかりの私にはその価値も魅力も分かりませんでした。小皿は机の引き出しに長く突っ込まれたままになってしまいましたが、思い出すのは村山さんの店に積み上げられていた品の山です。ひと月も経つとまた行きたくなり、数時間の道のりを出掛けて行きました。
訪問を重ね、やがて入れ替わる様にやって来るお客さんとも親しく言葉を交わす様になっていました。品探しのコツも身につけました。先ずはここ(村山さんのお店)にいっぱいあるそば猪口やくらわんかの中から、欲しいもの(買いたいもの)を選び出し、椅子の前にある小さなテーブルに借り置きし、それからじっくりと店内を物色します。数ヶ月に一度の訪問では、雑多に積まれた品にそう大きな変化はありませんが、見慣れた品々の中から、前回は気づかなかった(気づけなかった)骨董探しを再開します。お昼休みを挟んで夕方まで、特別の“何か”が見つかる訳ではないのですが、この時間が楽しいのです。探し疲れたら椅子に腰掛け、奥さん(お婆さん)が淹れてくれた茶をのみ、菓子器に盛られた菓子をつまんで……。村山さんは迷惑そうな顔もせず、淡々と接してくれます。ぽつりぽつりと身の上話をし、村山さんは「ほう、ほう」と楽しそうに頷いてくれます。
ないものを探すのではなく、あるもの(似たようなもの)の中から好みの1点を探す。そんな骨董探しの楽しみが実感できたのは、村山さんを訪ねてからのことです。
村山さんでの数千円から数万円の買い物で手元に集まったそば猪口類は、やがてデザイナーを目指して東京に出てきた私をしばらくは経済的にも助けてくれることになりました。
家業の牛乳屋に飽きてしまい、デザイナーになると、何のあてもなく東京へ出た私は、生活費に充てるため下宿先に近い団子坂(文京区)の骨董屋に、村山さんで買ったそば猪口数十個を買い取ってもらうことになりました。店主が提示してくれた買値は私が村山さんで支払った数倍ではなかったかと思います。当時、そば猪口ブームが到来し、全国の骨董店から目欲しい図柄のそば猪口が姿を消していた時代でした。数十個のウブくて珍しいそば猪口に骨董店主は喜んだでしょうが、私もそのお金で無職の日々をしのぐことができました。
*この連載は、高木孝さん監修、青花の会が運営する骨董通販サイト「seikanet」の関連企画です
https://store.kogei-seika.jp/

