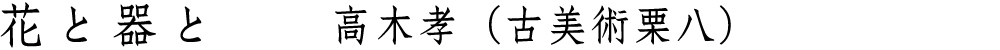
79 青銅古代金具

漢時代の青銅古代金具に落としを設えてもらい、花器としています。金具には当初より穴が穿たれており、掛け花入れには好都合です。深い緑青肌の古代金具で、エッジが効いており、小品ながらなかなかの存在感と古格があります。やさしい野花では器に負けてしまいそうで、斑入りのアメリカ蔦を花材として挿してみました。アメリカ蔦は名前のとおり北米原産の観葉植物だそうです。

村山さんのこと その2
ようやくたどり着いた柏崎の骨董店(村山さん)で見つけた素焼きの壺。それは雑然と積まれた品の並ぶ棚の片隅に、忘れられた様に置かれていました。値を訊けば「1万円」とのこと、ついに念願の六古窯が買えたと、喜び勇んで持ち帰りました。
壺は素焼きで薄茶色、肌の所々に剝落があります。底を見れば黒々と汚れています。信楽なのか常滑なのか、はたまた……と手元の骨董誌などを見ながらあれこれと思案するのですが、サッパリ分かりません。詮索をあきらめ部屋の隅に置いていると、ある日、母が目に止め、「その消し壺どうした?」と訊いてきます。?(ケシツボと確かに聞こえた……)私が「ナニ?」と応えると、「家にもあるろう」と言って戸を閉めました。
イヤな予感がして、物置のあちこちを探すと、ありました。もう少しきれいですが、薄茶の肌の、形もよく似た素焼きの壺が……。蓋が付いており、開けてみると底の方に細くなった消し炭が数本入っています。そういえば子供の頃、玄関(土間)にこの壺が置かれていた様な気がします。喜んで持ち帰ってきたのは中世六古窯ではなく、汚れた消し壺でした。
独り合点した私が愚かでしたが、時間が経つと、あの棚と広間にびっしりと積まれていた品々が思い浮かんできます。次回こそじっくりと探せば、何か嬉しい買いものができそうな予感がします。消し壺買いから数ヶ月後、再び柏崎まで出かけて行きました。今度は店にいる(物色する)時間に余裕を見ての、早めの出発です。
村山さんご夫婦は、私のことを覚えていてくれました。あの頃、20歳になったばかりの若者が骨董屋を訪ねて来て、店のあちこちを熱心に探しまわる光景はまずなかったのでしょう。骨董屋とはほとんどお客さんの来ない暇な商いと思っていた私は、村山さんの来客の多さにも驚きました。彼らはひと通りの挨拶が済むと棚から何かを取り出し、客用の椅子の前に置かれた小さなテーブルまで持ってきて、眺めたり、いじったりしながら、村山さんや顔馴染みと思われる相客と楽しそうに会話を交わしています。買わずに帰ってしまう客もいれば、何かを買って帰る客もいます。
そんな村山さんと来客との様子を眺めながら、私は〝何か探し″に余念がありません。が、何を買って良いのかわかりません。昼前に着き、途中お昼を食べに近所の食堂へ出かけ、また戻って来てはあれこれと物色を始め、もう日が暮れようとしています。何を買ったら良いのか、何が欲しいのか、実のところ自分でもわからないのですが、村山さんで雑多な品に囲まれながら〝何かを探している時間″が楽しくて仕方ありません。奥さん(お婆さん)は、ニコニコしながら「何かあったかね」と、何度も茶を注いでくれます。ひと息ついて茶を呑んでいると、村山さんが奥から小皿をひとつ手に持って出て来ました。私の前に置くと、今日のところは黙ってそれを買っていけ、と言います。それは普通の家にはない皿で、金持ちの家からしか出てこないものだと言います。染付のきれいな皿ですが、それがどの様なものか、どれほどの価値のものか私にはサッパリ分かりませんが、村山さんの言うとおりに、そのきれいな皿を買って帰ることにしました。挨拶を済ませ店を出ると、陽はもうすっかり落ちていました。
*この連載は、高木孝さん監修、青花の会が運営する骨董通販サイト「seikanet」の関連企画です
https://store.kogei-seika.jp/

