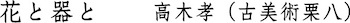
*この連載は seikanet(骨董通販サイト)の関連企画です
37 針金の新聞受

素人の手作りでしょう。太めの針金を編んだ方形の籠で、「セッション5」(骨董催事)の会場で見つけました。売主の説明によれば新聞受けだそうです。云われてみれば確かに新聞受けですが、飾られている時には、これに小さな人形(調べてみたらスパイダー人形と云うらしい……)が、十数個無造作に引っ掛けられており、出来損ないの人形用ジャングルジムにしか見えませんでした。とりあえずジャマな人形を取り除いてもらうと、思ったとおり、シンプルでモダンな、枯れた鉄味の立体(オブジェ)が現れました。最終日の午後に、そう高くもないこの新聞受けが売れ残っていた要因は、引っ掛けてあったあの人形であったことは間違いありません。私にとっては誠にありがたい人形たちであった訳です。売り主の画餅洞(わひんどう)さんは、さらに値引きまでして渡してくれました。「それ、売れ残ったら狙ってました」と、隣で商いをしていた大吉さんが言いました。正直な大吉さんですので、世辞ではなく本音でしょう。
花は風船葛の蔓一本です。栗八では階段の踊り場に、夏の日除け代わりに風船葛を毎年植えています。夏の盛りには密集して小山の様に膨らみますが、強い日差しの日中は萎れて得体の知れぬ青草の塊となっていますので、少々不気味です。

吉村公三郎監督のこと その3
「第4回 日本映画の発見 吉村公三郎ノ世界」のパンフレットに、今村昌平監督がこのように書いています。
───
昭和26年(1951年)、私が松竹大船撮影所に入った時、吉村監督はもう松竹には居られず、確か大映で仕事をなさっていた。
しかし、吉村さんに関わるエピソードは、助監督やスタッフ間に語り伝えられていた。 エピソードというものは、とかく面白おかしくオーバーになりがちなので真偽の程は判ら ないが「少々つまらないシナリオでも、やりようによっては一流の映画になるものだが、 要はコンテなのだ」と吉村さんが語ったという話は、私には本当らしく思えた。しかしシ ナリオが映画の70%を決めると思いこんでいた私は「要はコンテ、つまり演出なのだ」ときいて驚いた。
勿論、演出家になりたいと思って大船に入ったのだから演出の力を信じたい。演出力をコンテ力とする考えにはにわかに賛同できなかった。演出はコンテとイコールではない、 コンテに書き切れない要素だってある筈だ。その頃小津安二郎組の四番目の助監督だった私は、コンテの勉強なんかまるでしなかったのである。
あるチーフ助監督と飲んでいたら「君はコンテの勉強をしてるかね?」といきなり訊かれた。「いえ別に……」「 演出家をめざす者がコンテを学ばなくてはダメだ。コンテはシナリオでは書き切れないところを具体的に表現し、演出のリズムを決めるのだ。 好きな映画のコンテを取ってみるのは良い勉強だ、外国映画でも何でも良い。だが吉村さんの映画だけは君が好きだろうと嫌いだろうとコンテの勉強の手本にすべきだ」
私はついにコンテの勉強をしなかった。が、若い人たちの勉強の対象として「第4回 日本映画の発見」に吉村映画を選んだ。演出とコンテの冴えを観て欲しいのである。
小むづかしい映画ではない。一般の方々にも楽しんで頂きたい。(今村昌平「仕掛人の弁」)
───
如何ですか、なかなか一映画ファンには分かりにくい内容ではあるのですが、要は「あの脚本では……」とか「あの撮り方は……」と云った、映画好きの酷評を跳ね返すだけの力(演出力)を、吉村公三郎作品は持っていたと云うことなのでしょう。それがどの様な場面で活きているのかは、素人の私には理解しにくいのですが、吉村公三郎監督(以下監督)に直接お会いして、映画の細部にちりばめられている様々な秘密(斬新な演出技法)をうかがったあとでしたので、技の冴え(コンテ力)については、素人なりに理解できました。監督自身は、パンフレットにこう書いています。
───
松竹キネマ蒲田撮影所での助手時代、この十年は本当に辛い十年でした。 時にはぶんなぐられることもあったので、「殴られる彼奴」の綽名もついたのです。撮影所が大船に移り、私は助監督十年目にやっと監督になることが出来ました。あれ程私の監督昇進を待ち望んでいた父母は五年前すでに他界しておりました。監督になって五本目の作品で、全く偶然のことから『暖流』というのを監督し、これでどうやら世間にもいくらかみとめられるようになり、それから以後映画を作りつづけ、今日に至っております。
『暖流』がいくらかマシな映画になったのは、先ず池田忠雄さんの脚本の出来がよかったこと、出演している高峰三枝子さん、水戸光子さんに魅力があったことです。 実際、彼女達はそれぞれの生涯で最も美しいときでした。私は彼女達の美しさにささえられたのです。
もっとも監督の私にとってもはじめての特作品でしたので、それまで助監督のながい年月、ああもやろう、ああもしたいとの意欲を全部さらけ出したことでした。それに何よりも若さも手伝っていたのです。
それからの五十年の間に六十本の映画をとりました。監督の仕事は勿論愉しいこともありましたが、才能の乏しい私には寧ろ苦労の多い年月でした。
───
『暖流』が撮られたのは戦前(1939年)です。自立する女性を斬新な描き方(撮り方)で見せており、一躍評判となったそうです。『暖流』の鮮度は、80年以上過ぎた今観ても失われていませんから、やはり傑作ですね。
さて、ヒット作『暖流』を撮って以降の監督についてです。これに関して、戦前から松竹で共に映画作りに携わってきた脚本家である新藤兼人が、パンフレットに一文を寄せています。面白いエピソードですので一部を紹介します。
───
『森の石松』を封切って、松竹首脳はあっとおどろいた。映画館ががら空きなのだ。わたしもおどろいた。かなりヒットするだろうと思ったからだ。作品は吉村作品では白眉のものとなった。爆発するようなエネルギーが一コマの隅々までみなぎっていた。
森の石松に戦後の若もの像を擬した。砕け散った凄絶な末路が観客をはじき返したのであろうか。大衆は戦後の暗いきびしさから脱出しようとしていた。(略)
これがきっかけとなって吉村・新藤コンビの解消が囁かれはじめた。コンビといわれたのは『安城家の舞踏会』『誘惑』『わが生涯のかがやける日』『嫉妬』と順調に興行成績をあげてきたからである。『森の石松』につづいて、『真昼の円舞曲』『春雪』がまた営業部の期待を裏切り、次回作品に『肉体の盛装』を準備していたが、ストップがかかった。 (略)
コンビを解消させたほうがいい、吉村公三郎を駄目にしてしまう、という声を聞いて、あっと熱が醒め、外へ出て仕事をする気になった。そのことを吉村氏に伝えると、俺も松竹を出たいという。覚悟ができているふうだった。
吉村監督は松竹子飼いの監督で『暖流』で知られるように数々の儲かる仕事をしてきたドル箱監督である。やめたい、というからにはよほどのことがあったのであろう。 企業の束縛をはなれて、自由に仕事をしてみたい渇望がわたしたちにはあった。ちょうど戦後の独立プロ乱立時代で、わたしたちもその風にあおられた形となった。独立プロ近代映画協会を興したのである。
松竹をやめる直接のきっかけとなった『肉体の盛装』をいやでも実現させねばならなかった。
大映、東横 (東映の前身)へ持ち込んだが、大映は川口松太郎専務が、芸者物はうけない、と一蹴。東横では、内容がうちのものではない、と断られた。外の壁は厚かった。自由の風は甘くはなかった。(新藤兼人「その前夜」)
───
フリーランスでの映画製作の厳しさや、商業主義優先の映画会社のドライな対応が綴られており、興味深いのですが、両名は独立から間もない1951年に大映京都で『偽れる盛装』(『肉体の盛装』を改題)を撮り、その年のキネマ旬報第3位、毎日映画コンクール監督賞、脚本賞、ブルーリボン賞等を獲得しています。監督は、それ以降も様々な映画会社の依頼で、当時の大スターを起用したヒット作を次々と撮っています。この事実(実績)こそが、映画監督吉村公三郎の実力なのです。監督はパンフレットに寄せた一文の最後にこう書いています。
───
さて、今つくづく考えてみますと、真に映画を愉しんだのは、映画製作に携わる以前で、それ以後になると、映画をみても実際の仕事に関連させて観るので、愉しさとは程遠いものになりました。
近頃になって年令のせいもあり、健康状態も思わしくなく、体力気力共に衰えて来て、映画製作から遠ざかるようになり、又再び映画を観る愉しみにもどった訳ですが、今度は映画の方が内外ともにつまらなくなって来ました。
最近、今井正監督の『戦争と青春』というのを観せてもらいました。近頃の日本映画としてはなかなかよく出来ていて、私と同年配の今井さんの努力に感心しましたが、それでも嘗っての『キクとイサム』のような引きしまった作品ではありませ んでした。残念に思います。
───
映画祭が終わって後のことです。お会いした日の帰りがけ、俳句の話題となり、その場でいくつか監督の句を見せていただきました。私が「好きです」と伝えていた句が、簡潔な礼状と共に、色紙に書かれて送られてきました。
朝顔にただ水をやる男なり 公三郎
「これ一本」(キャッチフレーズ)が思いつかず、苦労した仕事でしたが、思い出深いものとなりました。
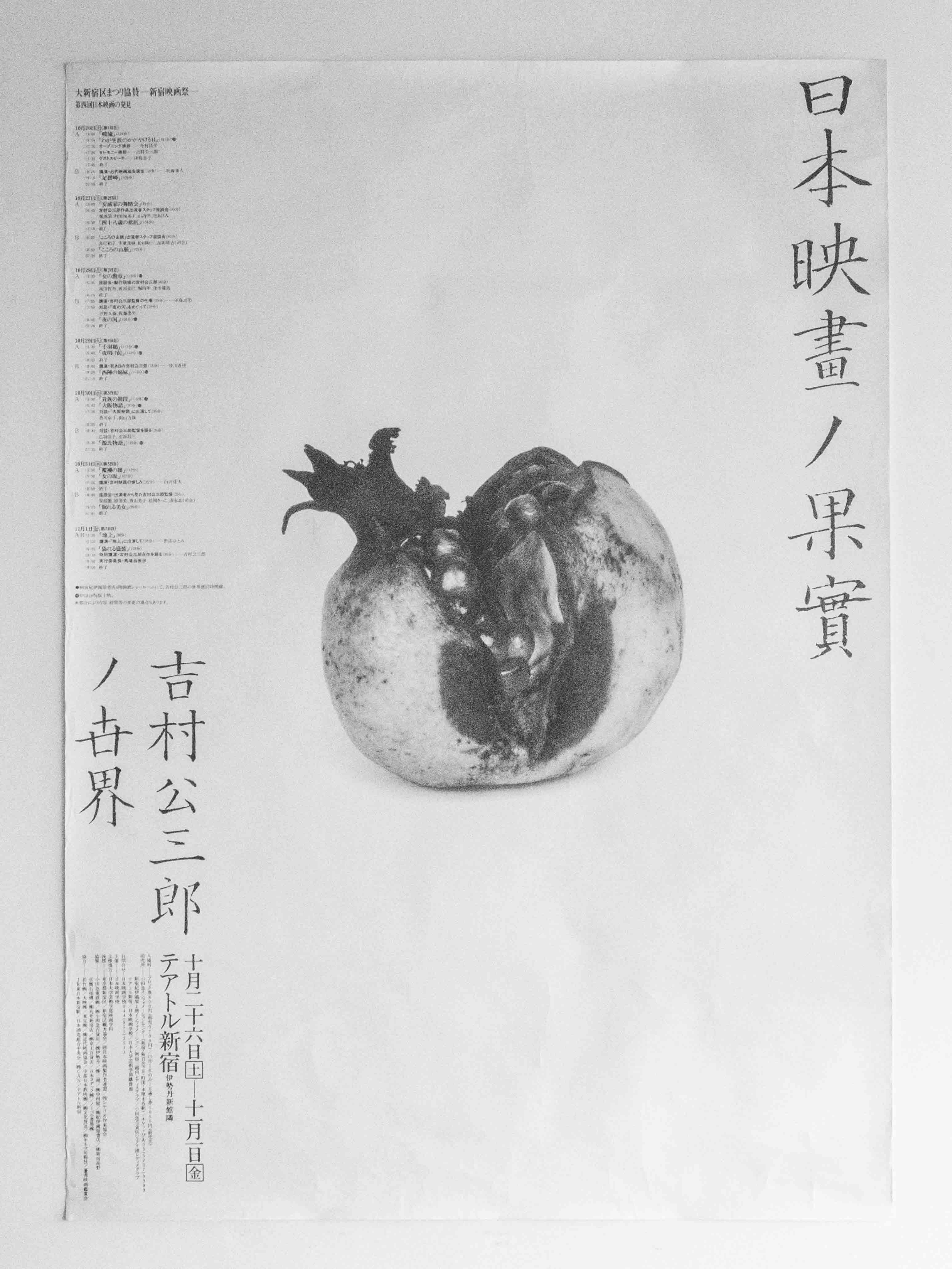
https://store.kogei-seika.jp/

